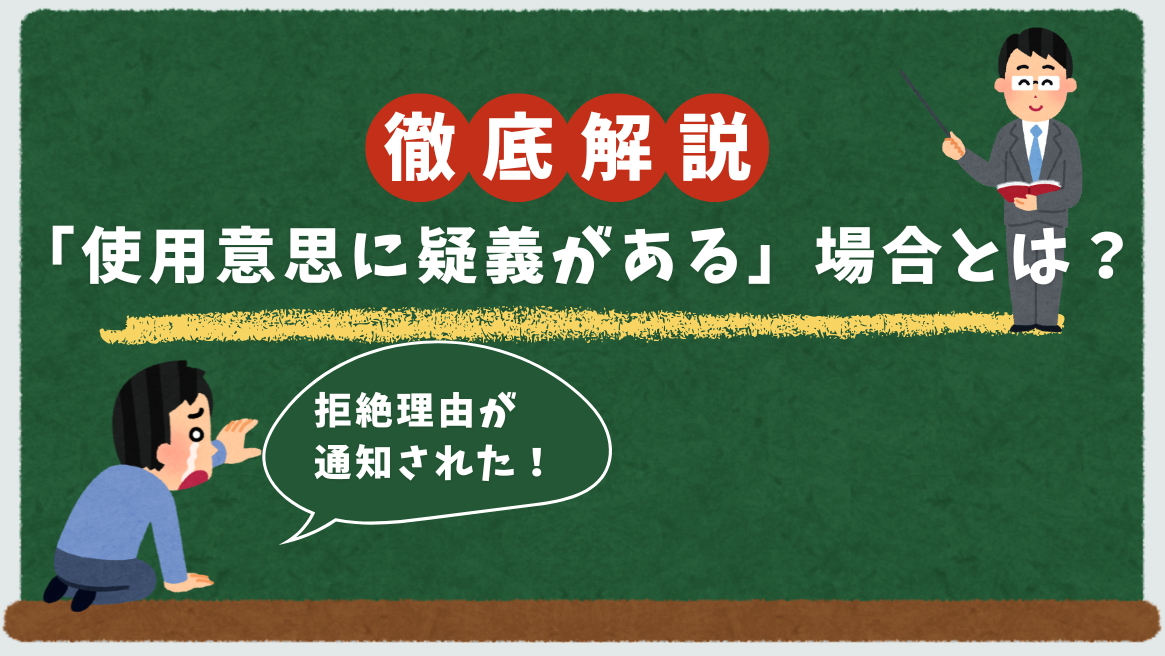商標出願をしたにもかかわらず、「使用意思に疑義がある」として拒絶理由通知を受けるケースがあります。
「使うつもりで商標出願したのに、なぜ?」と驚かれる方も少なくありません。
特許庁の審査では、指定商品・役務と実態との整合性や類似群コードをもとに、厳しく判断されることがあります。
本記事では、拒絶理由としての「使用意思に疑義あり」とはどういうことか、どのようなケースで判断されるのか、具体例とあわせて弁理士の視点で解説します。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・これまで、膨大な量の拒絶理由通知の対応をお手伝いしました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
出願商標の使用意思に疑義があると、拒絶理由通知書で指摘!?
あなたが、商標出願して、特許庁の審査官が商標登録を認めないと判断した場合には、拒絶理由通知書が届きます。
拒絶理由通知書が届いたら、以下の記事を参考にして、拒絶理由通知の内容を確認しましょう。
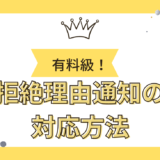 拒絶理由通知書の対応方法|商標登録をあきらめないためにできること
拒絶理由通知書の対応方法|商標登録をあきらめないためにできること
よくある拒絶理由として、出願商標の使用意思に疑義があるため、出願商標が商標法3条1項柱書の要件を具備しないという理由が挙げられます。
それでは、どのような場合に、出願商標の使用意思に疑義があると判断するのでしょうか?
特許庁の審査で、出願商標の使用意思に疑義がある場合とは
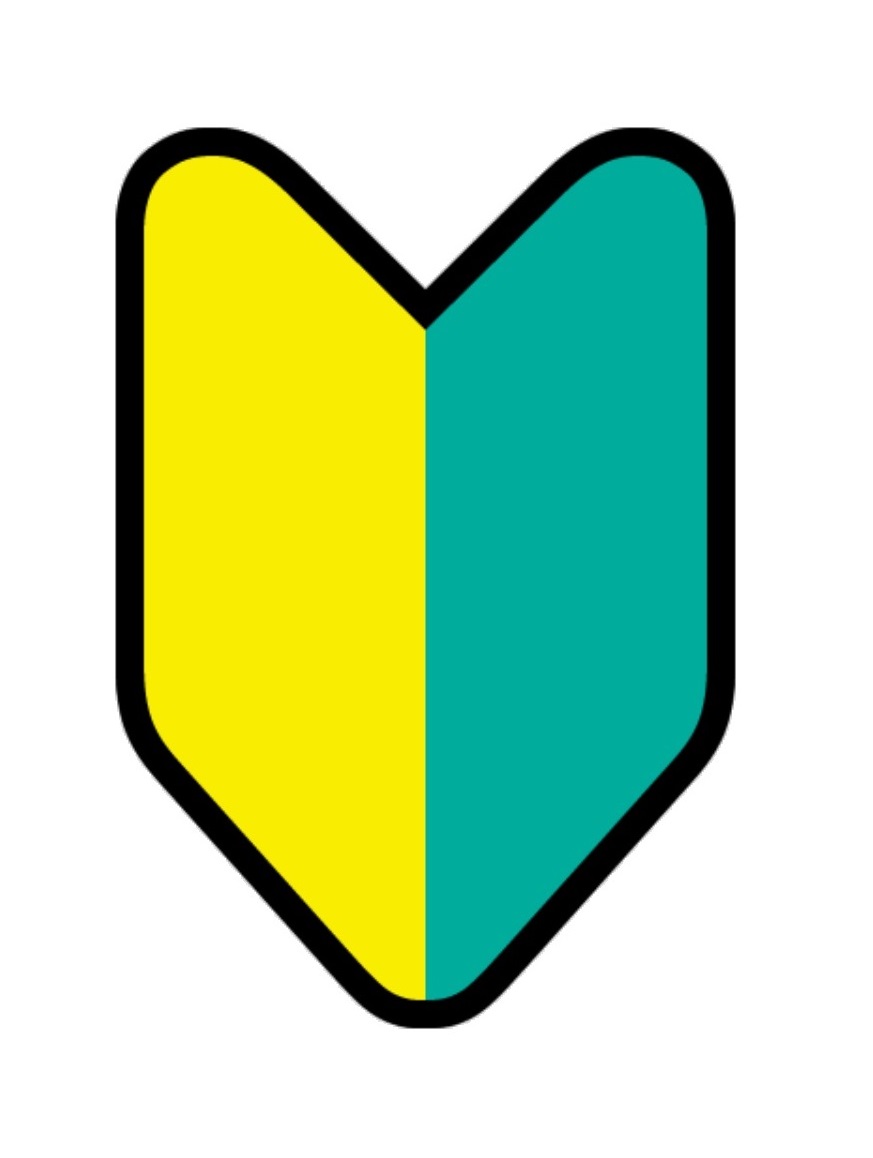
特許庁の審査で、出願商標の使用意思に疑義あると、どのように判断しています?

特許庁の審査では、1区分に含まれる類似群コードの数によって、自動的に、判断しています!
類似群コードについては、以下の記事で、簡単に説明しているので、参照ください。
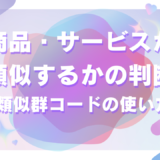 商標登録で失敗しないために!商品・役務の類否判断と類似群コードの使い方
商標登録で失敗しないために!商品・役務の類否判断と類似群コードの使い方
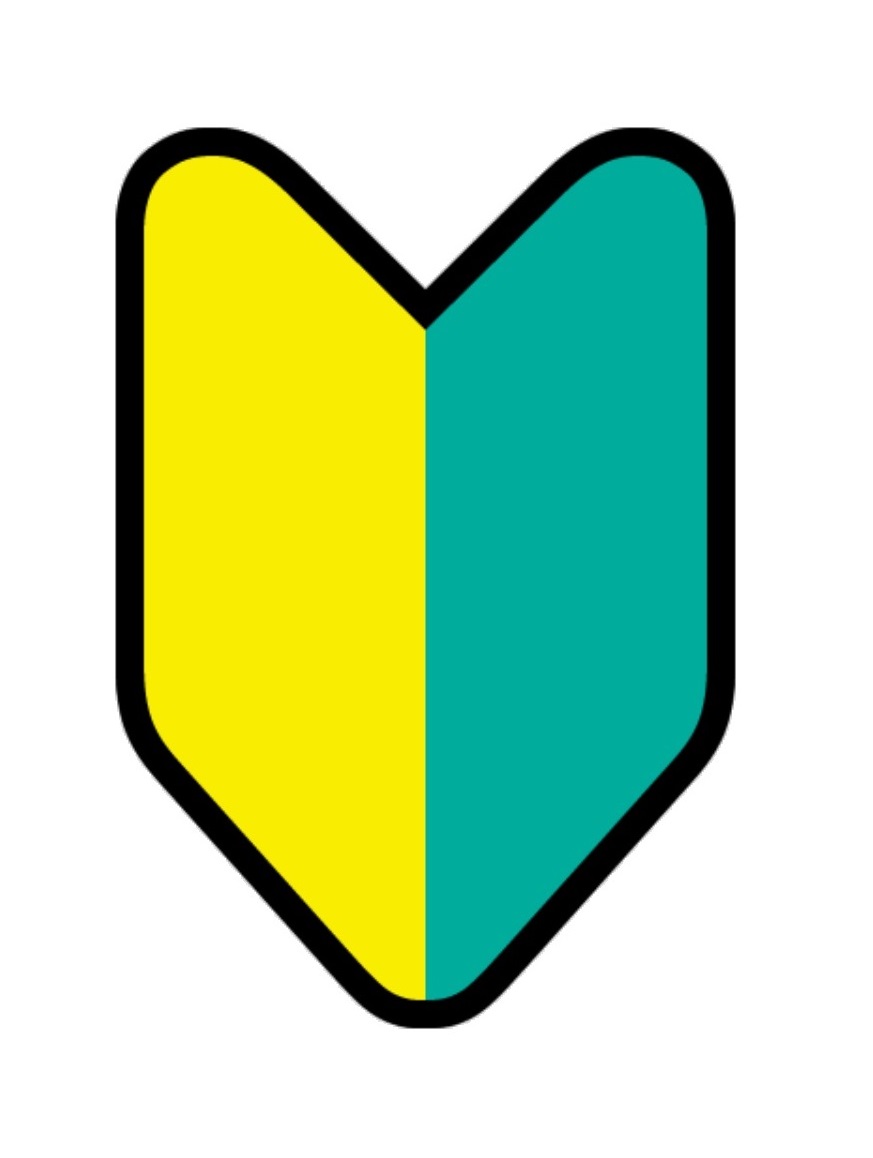
出願商標の使用意思に疑義あると、具体的に、どのようなケースですか?

原則として、1区分内において、23以上の類似群コードにわたる商品・役務を指定している場合、それらの指定商品・役務について、使用意思に疑義があると判断されます!
すでに商標出願している場合、データベース「J-PlatPat」で検索すれば、類似群コードが記載されているので、類似群コードの数を簡単にカウントすることができます。
また、このような拒絶理由を避けたい場合、データベース「J-PlatPat」などを利用して、商品・役務が付されている類似群コードを推測することで、類似群コードの数を予想できます。
例えば、あなたが、3類と41類を指定して商標出願したとします。
3類の指定商品の類似群コードの数は計7個だったのに対して、41類の指定役務の類似群コードの数が計25個だったとします。
その場合には、23以上の類似群コードを有する41類の指定役務についてのみ、出願商標の使用意思に疑義があると判断されます。
【注意!】35類の小売等役務を指定した場合は、より厳格に判断
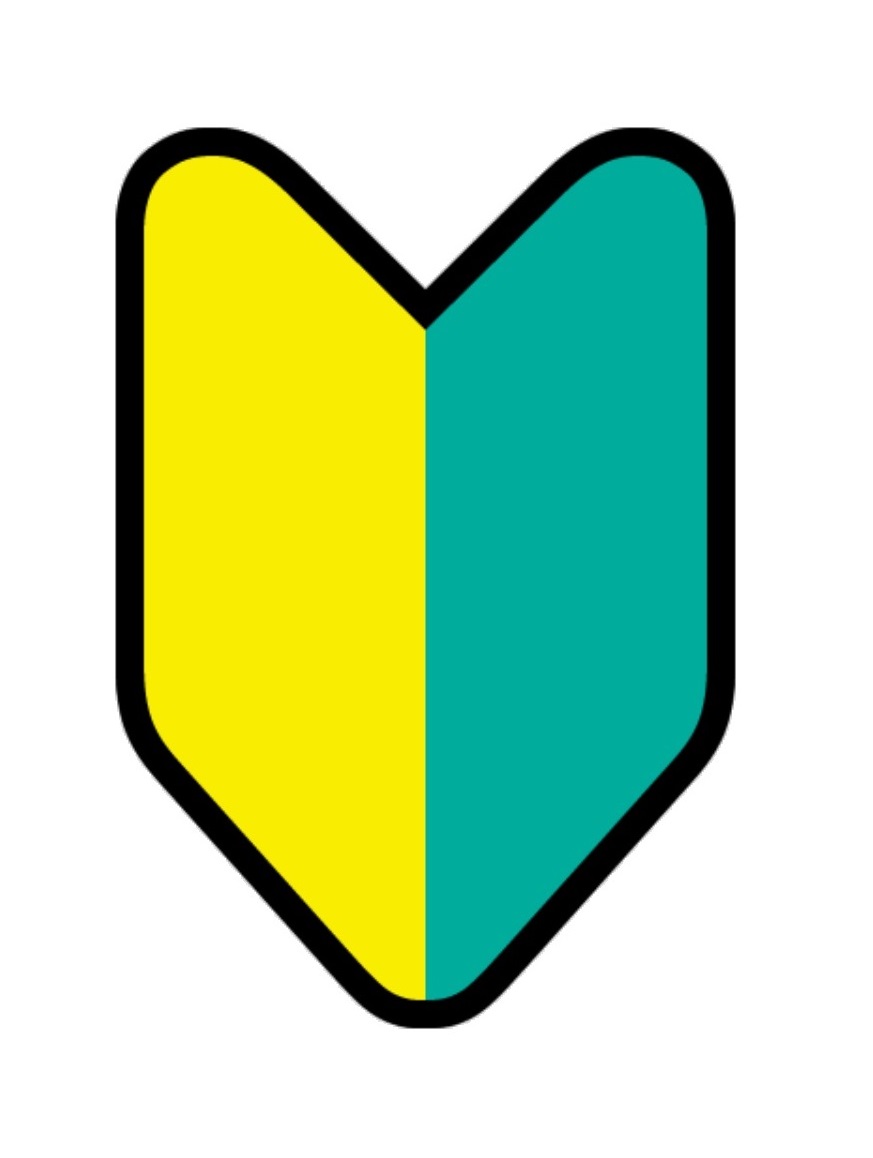
より厳格に判断されることはありますか?

35類の小売等役務を指定した場合には、使用意思に疑義があるか、より厳格に判断されます!
35類において、様々な商品の小売等役務を指定することができ、小売等役務の場合、判断方法は、一般の商品・役務と異なります。
なお、小売等役務の概要については、以下の記事で詳しく紹介してます。
 初心者向け|商標法上の「小売等役務」の意味と注意点を解説
初心者向け|商標法上の「小売等役務」の意味と注意点を解説
【具体例を使って、解説!】
例えば、帽子の小売等役務であれば、「17A07」と「35K02」の2つの類似群コードが付き、化粧品の小売等役務であれば、「04C01」と「35K10」の類似群コードが付きます。
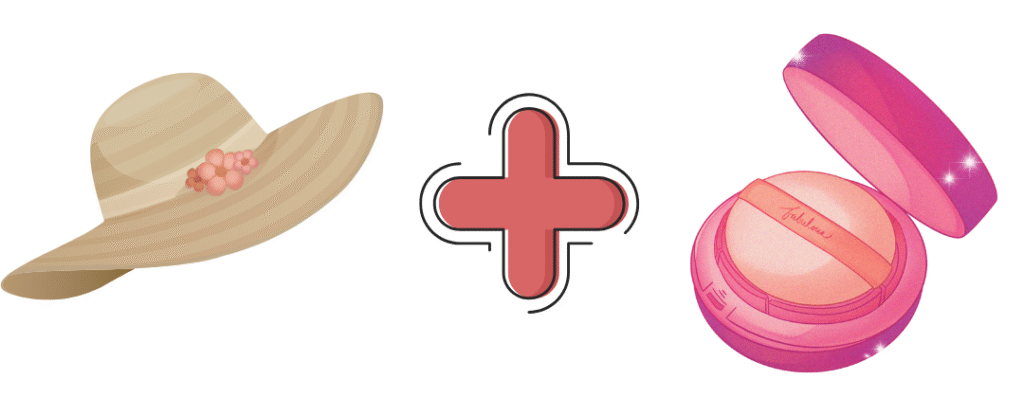
35類において、「35K」から始める小売等役務の類似群コードが複数ある場合、原則、使用意思に疑義があると判断されます。
具体的には、帽子の小売等役務と化粧品の小売等役務を指定して商標出願した場合には、「35K02」と「35K10」の小売等役務の類似群コードを含みます。
よって、特許庁の審査において、使用意思に疑義があるという、拒絶理由が通知されます。
一方で、「35K」から始める小売等役務の類似群コードが1つだけであれば、原則、使用意思に疑義があるとは判断されません。
例えば、帽子の小売等役務とかばんの小売等役務の2つを指定して、商標出願したとします。
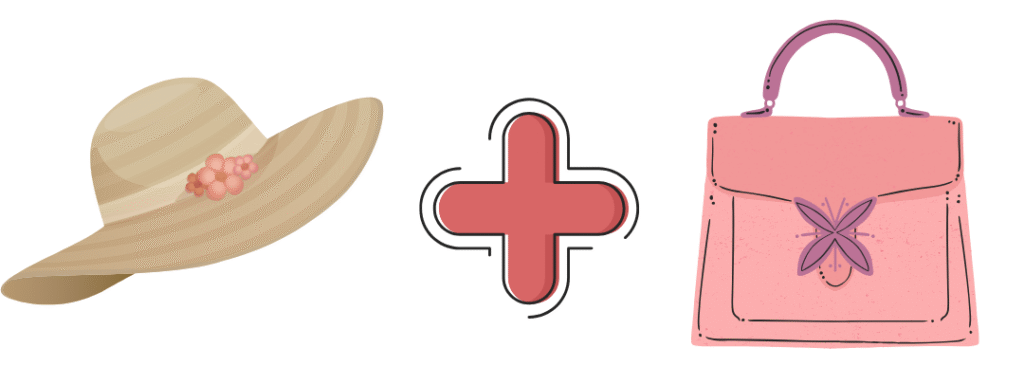
帽子の小売等役務の類似群コードは「17A07」と「35K02」、かばんの小売等役務の類似群コードは「21C01」と「35K02」です。
よって、この場合、小売等役務の類似群コードは「35K02」だけなので、使用意思に疑義があると判断されません。
【例外を紹介!】
なお、例外を説明すると、35類には、以下の総合小売等役務(類似群コード35K01)があります。
衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
例外的に、総合小売等役務を指定した場合、類似群コードの数に関係なく、使用意思に疑義があると判断されます!
現行の「出願商標の使用意思の疑義」の特許庁の審査運用
使用意思に疑義があるかどうかの審査運用は、商標審査便覧に細かく規定されています。
ざっくりと言えば、原則、1区分内の類似群コードの数が23以上の場合には、自動的に、その区分の指定商品・役務について、使用意思に疑義があると判断します。
基本的には、1区分の中に含まれる指定商品・役務の類似群コードの数が重要です。
ただし、35類の小売等役務については、例外的で、「35K」から始める小売等役務の類似群コードが複数ある場合には、原則、使用意思に疑義があると判断されます。
「出願商標の使用意思」のよくある質問(FAQ)
以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。
記事本文と合わせてご活用ください。
特許庁の審査で、指定商品・役務について、本当に出願商標を使用する意思があるのか、疑われる状態を指します。
1区分の中で、広範囲に商品・役務を指定した場合などに、審査官がその意思を疑う可能性があります。
記事本文で説明した通り、特許庁の審査では、類似群コードの数で、自動的に判断します。
具体的には、1区分内において、23以上の類似群コードにわたる商品・役務を指定している場合、使用意思に疑義があると判断されます。
また、小売等役務の場合、「35K」から始める類似群コードが複数あると、使用意思に疑義があると判断されます。
使用意思に疑義があると判断されると、拒絶理由通知を受けて、審査がストップします。
また、反論や補正が認められなければ、商標登録できない危険性があります。
例えば、以下の方法で、拒絶理由を解消できます。
- 対象の区分において、一部の指定商品・役務を削除
- 使用している事実を示す証拠資料を提出
- 使用宣誓書と事業計画書を提出
詳しくは、以下の記事内で、解説しています。
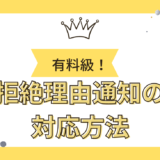 拒絶理由通知書の対応方法|商標登録をあきらめないためにできること
拒絶理由通知書の対応方法|商標登録をあきらめないためにできること
【まとめ】出願商標の使用意思に疑義があると判断されたら、商標専門の弁理士に相談!
・原則、1区分内の類似群コードの数が23以上の場合には、自動的に使用意思に疑義があると判断します
・35類の小売等役務については、例外的で、「35K」から始める小売等役務の類似群コードが複数ある場合には、原則、使用意思に疑義があると判断します
・さらに、総合小売等役務を指定した場合には、類似群コードの数に関係なく、原則、使用意思に疑義があると判断します
拒絶理由通知書において、出願商標の使用意思に疑義があると判断されて、判断に不満がある場合もあるでしょう。
その場合には、担当の審査官に連絡すれば、理由を丁寧に教えてくれます。
また、商標専門の弁理士に相談するのも、アリです。
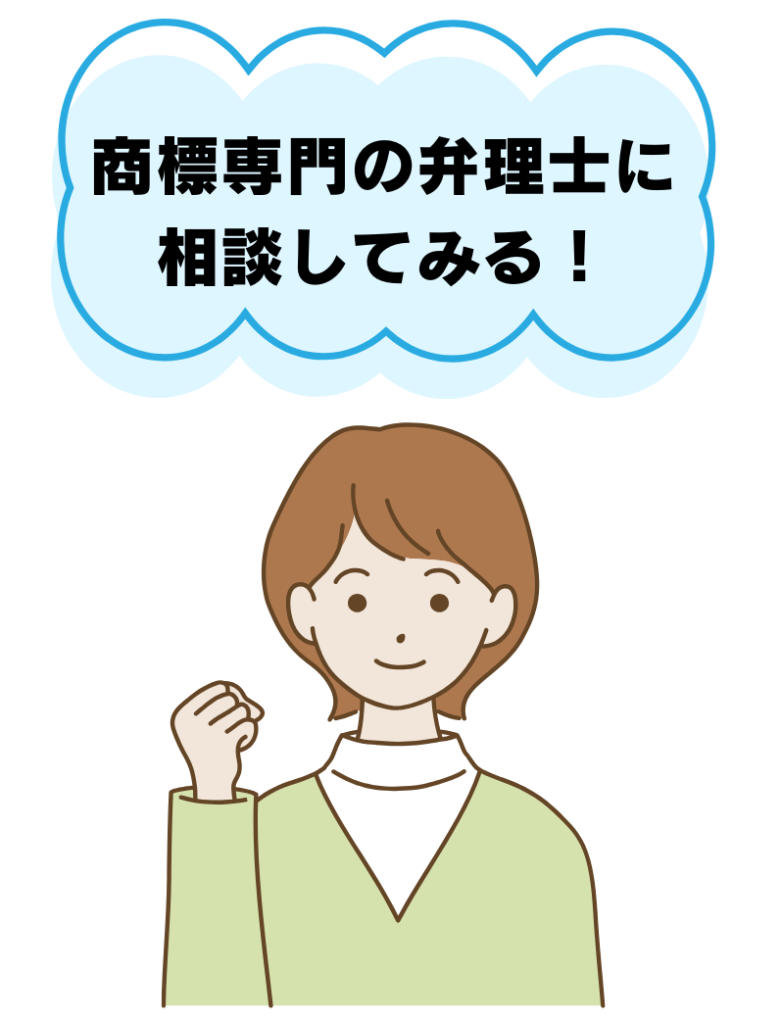
筆者(角谷 健郎)にご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します。
また、拒絶理由通知の応答から、手続きを代理することもできます。
事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。