「読み方が似ている商標は登録できないって本当?」
商標の登録可否は、「見た目」や「意味」だけでなく、呼び方(称呼)が似ているかどうかも重要な判断ポイントです。
たとえば、発音が近い商標同士は「称呼が類似」と判断され、登録が認められない場合があります。
この「称呼の類似」は、商標審査で最も頻繁に問題になる要素のひとつですが、判断基準や具体的な類似例を知らないと、せっかくの商標出願が拒絶されてしまうことも少なくありません。
本記事では、称呼類似の判断基準や事例を、弁理士の視点からわかりやすく解説していきます。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・これまで膨大な量の商標案件を担当し、商標の類否の相談を受けてきました
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
商標の類否は、商標から生じる外観・称呼・観念の3つの要素から判断!
以下の記事で、商標の類否判断基準について、紹介しました。
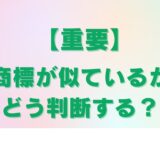 商標が似ていると登録できない?類否の判断基準と具体例を紹介
商標が似ていると登録できない?類否の判断基準と具体例を紹介
商標の類否は、商標から生じる外観・称呼・観念の3つの要素から判断します。
それでは、称呼が類似しているのは、どういった事例になるでしょうか?
特許庁が公表している商標審査基準をもとに検討していきます。
称呼の類否の判断方法
まず、称呼の類否の判断方法について、説明します。
商標審査基準によると、両称呼の音質、音量及び音調並びに音節が判断要素になります。
これらの判断要素が共通したり、近似するところがあるか否かを比較します。
また、商標が称呼され、聴覚されるときに、需要者に与える称呼の全体的印象も重要になり、称呼の全体的印象が、互いに紛らわしいか否かを考察します。
次に、商標審査基準で例示している称呼類似の事例を確認していきます。
商標から生じる称呼が類似する例(商標審査基準より)
商標審査基準には、称呼類似の例示が多く記載されていますので、その中から抜粋して、重要なものを紹介します。
①同数音の称呼からなり、相違する1音が清音、濁音、半濁音の差にすぎない場合
例:「ビュープレックス」と「ビューフレックス」
例:「バーテラックス」と「バーデラックス」
②相違する音が長音の有無にすぎない場合
例:「モガレーマン」と「モガレマン」
③相違する音が促音の有無にすぎない場合
例:「コレクシット」と「コレクシト」
④相違する1音がともに弱音である場合
例:「シーピーエヌ」と「シーピーエム」
⑤弱音の有無の差にすぎない場合
例:「デントレックス」と「デントレック」
⑥比較的長い称呼で1音だけ多い場合
例:「ビタプレックス」と「ビプレックス」
商標の称呼の類否判断における注意点
実務上、商標の類否判断において、称呼が類似するか否かが、最も重要なポイントになります。
しかし、称呼の類否判断は、時代によって、傾向が異なります。
最新の判例や審判事例を紹介していきますので、類否判断の傾向を把握するために、参考にしてください。
・称呼(読み)は、商標の類否の判断要素の1つになります
・最近の傾向や商標審査基準を参考にしながら、称呼が類似するか、検討しましょう
・判断に迷う場合には、できれば、弁理士に相談することをお勧めします
なお、称呼の類否判断に迷った際には、商標専門の弁理士に相談しましょう
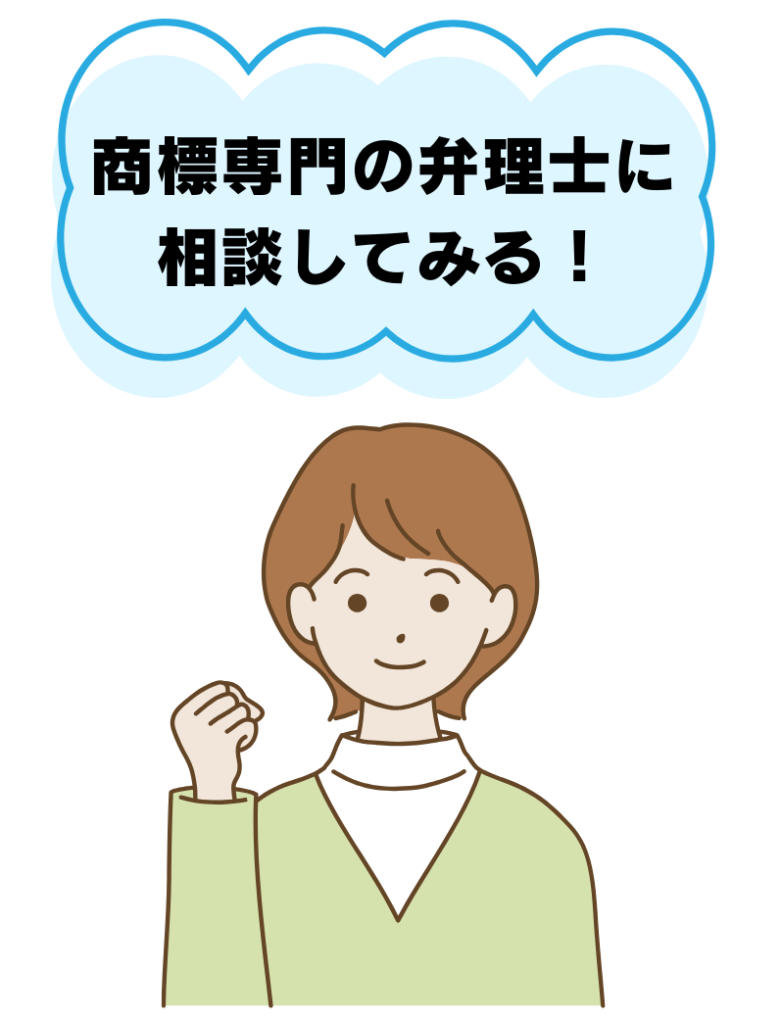
筆者(角谷 健郎)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討し上で、長年の経験をもとに、正確に判断します!
事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単に問い合わせいただけます。


