学習塾や通信教育などの教育ビジネスにおいて、塾名やブランド名は「顔」となる大切な資産です。
ですが、その名称を放置していると、他人に先に商標登録されてしまうリスクがあります。
特にフランチャイズ展開やオンライン講座の拡大を考えている場合は、早めの商標対策が欠かせません。
この記事では、学習塾や教育関連サービスを対象に、商標登録すべき区分(41類)や、実際に登録されている事例を弁理士の視点で解説します。
「どの区分を選べばいいの?」「塾名でも商標登録できる?」
そんな疑問にお答えしながら、教育業に必要な商標知識をわかりやすくまとめています。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています
・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています
・教育事業の商標登録をお手伝いした経験が多数あります
・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です
学習塾(教育事業)の商標登録で、出願すべき区分は41類
あなたが、学習塾を設立しようとしていて、塾の名称を商標出願したいと考えています。
それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、学習塾の名称を商標出願しますか?
教育事業では、何らかの知識を生徒に教えて、その対価として、授業料などを得ることで、成り立っています。
つまり、教育事業のメインとなるサービスは、「知識の教授」です。
「知識の教授」が属する区分は41類です。
よって、学習塾の名称を商標出願する場合には、少なくとも、41類をカバーする必要があります。
なお、教室には行かない通信教育の場合でも、知識を教授しています。
このような場合でも、41類がメイン・必須の区分になります。
また、教育事業に伴って、書籍を販売することが考えられます。
その場合、紙媒体での書籍は9類に属し、電子媒体での書籍は16類に属します。
学習塾(教育事業)で参考になる商標登録例
例えば、以下のような商標は、41類のみで、商標登録を取得しています。

※大学進学向けの予備校
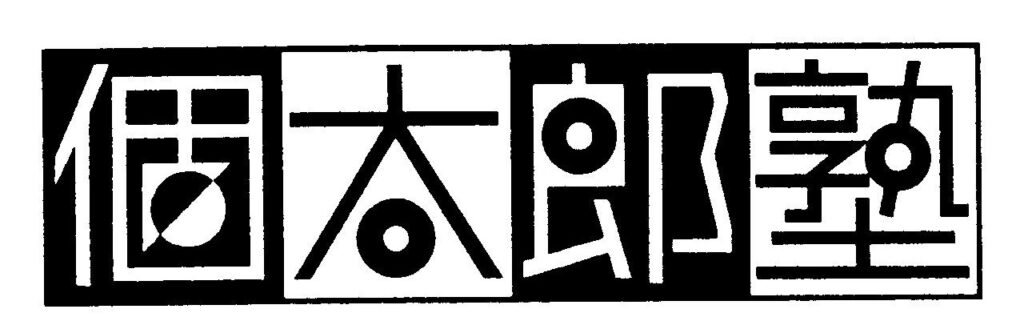
※個別指導の学習塾

※資格取得のための総合スクール
一方、以下の商標は、41類の他に、9類(電子出版物など)や16類(印刷物など)もカバーしています。
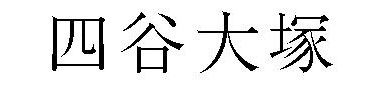
※中学受験のための学習塾

(商登第5661409号、区分:9類、16類)
※大学受験のための大手の予備校

(商登第3037982号、区分:41類)
※なお、2022年に「お茶ゼミ√+」に名称変更
なお、「やる気スイッチ」のテレビCMでお馴染みのスクールIEは、41類だけではなく、35類もカバーしています。

スクールIEは、フランチャイズで運営しています。
よって、35類では、以下のような役務を指定しています。
フランチャイズ方式による個別指導学習塾事業の運営及び管理並びにその経営の診断及び指導
このような登録例からも分かる通り、41類が、学習塾などの教育事業の基本・必須になります。
その上で、事業内容や予算に合わせて、必要ならば、その他の区分の追加を検討しましょう。
・「知識の教授」が属する41類が、教育事業のメインで、必須の区分です
・9類(電子出版物など)や16類(印刷物など)も指定することが考えられます
・事業内容や予算に応じて、41類以外の区分の追加を検討しましょう
学習塾などの教育事業での商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!
学習塾などの教育事業で商標登録する際、分からないことがあれば、商標登録の専門家(弁理士)に相談しましょう。
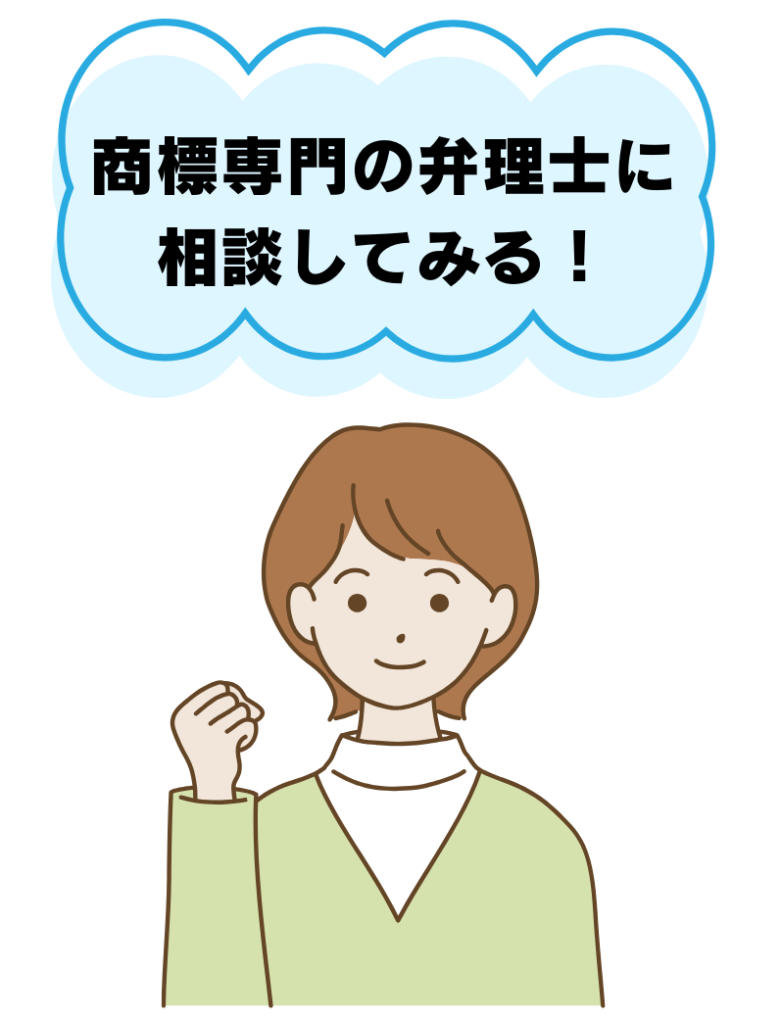
なお、筆者(角谷 健郎)は、数多くの教育事業の商標登録を手伝った経験があります。
ご相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。
事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。


